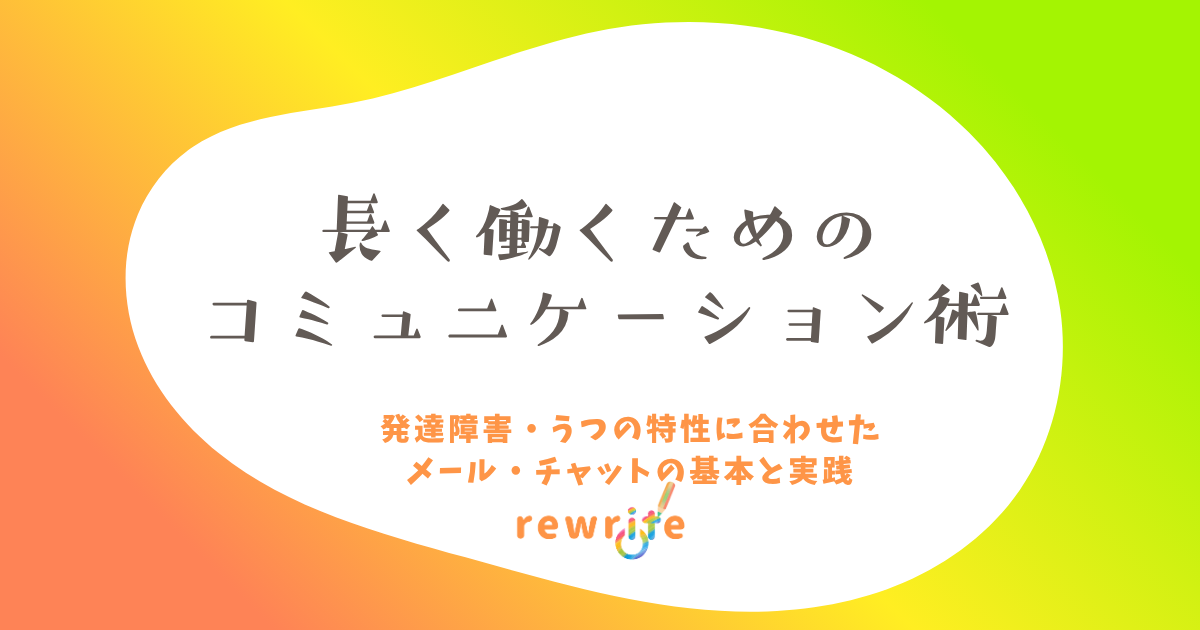
「メールを送る前に何度も読み返してしまい、時間がかかりすぎる」「チャットで意図が伝わらず、誤解されてしまった」「ケアレスミスで叱責され、自信をなくしてしまった」
うつやADHD、ASDなどの特性により、職場のコミュニケーションでつまずき、早期退職を経験された方にとって、次の就職は大きな不安を伴うものかもしれません。「次こそは、無理なく長く働きたい」と願うのは当然のことです。
特に、顔が見えないメールやチャットでのやり取りは、些細なことで誤解を生みやすく、ストレスの原因になりがちです。しかし、適切な方法を知れば、これらのツールはむしろあなたの強力な味方になります。
コミュニケーションは、生まれ持った才能ではありません。正しい「型」と「準備」を身につけることで、誰でも上達できるスキルです。この記事では、あなたの特性に寄り添い、明日からすぐに実践できる具体的なコミュニケーション術を解説します。
まず、なぜテキストコミュニケーションが難しいと感じるのか、その背景にある特性を理解することから始めましょう。自分を責めるのではなく、客観的に原因を知ることで、効果的な対策が見えてきます。
ADHDの特性がある場合、頭の中に次々とアイデアや考えが浮かび、話が飛びやすくなることがあります。これを順序立てて文章にするのは、多大なエネルギーを要します。一方、ASDの特性がある方は、細部に意識が向きやすく、全体像や要点を先に伝えるのが苦手な場合があります。口頭の会話であれば相手の反応を見ながら軌道修正できますが、一度きりの発信で完結させる必要があるメールでは、この「文章を組み立てる」プロセスが大きな壁となるのです。
テキストコミュニケーションでは、相手の表情や声のトーンといった非言語情報が一切ありません。そのため、「この表現で失礼にならないか」「冷たいと思われないか」といった不安が生まれやすくなります。特に、ASDの特性で相手の意図を汲み取るのが苦手だったり、うつ状態でネガティブな思考に陥りやすかったりすると、相手の反応を過剰に悪く想像してしまい、メールを1通送るのに何時間もかかってしまうことがあります。
ADHDの特性である不注意や衝動性は、テキストコミュニケーションで「うっかりミス」を引き起こす一因です。例えば、重要なメールの返信を忘れてしまったり、宛先を間違えたまま送信ボタンを押してしまったりといった経験はないでしょうか。これは、ワーキングメモリ(情報を一時的に記憶し処理する能力)の特性が関係していると考えられています。「後で返信しよう」と思って他の作業に移ると、メールの存在自体を忘れてしまうのは、決してあなたの意欲が低いからではないのです。
原因がわかったら、次は具体的な対策です。ここでは、どんな場面でも応用できる「基本の型」を3つ紹介します。この型を身につけるだけで、コミュニケーションの心理的負担は大きく軽減されます。
ビジネスコミュニケーションの基本は「結論から先に伝える」ことです。これは、思考がまとまりにくい特性を持つ方にとって、特に有効な手法です。伝えたいことを最初に一文で言い切ることで、相手に意図が明確に伝わり、自分自身も話の軸がぶれにくくなります。
このPREP法を意識するだけで、文章が格段に分かりやすくなります。
毎回ゼロから文章を考えると、それだけで疲弊してしまいます。よく使う連絡については、自分だけのテンプレートを用意しておきましょう。これにより、考えるエネルギーを最小限に抑え、ミスも減らすことができます。
件名:【ご報告】〇〇の件(自分の名前)
本文:
〇〇さん
お疲れ様です。〇〇です。
ご依頼いただいていた〇〇の件、完了しましたのでご報告いたします。
ファイルは下記に保存しております。
(ファイルパスやURL)
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
衝動的に送信ボタンを押してしまうのを防ぐために、物理的なチェックリストを作成し、指差し確認する習慣をつけましょう。Gmailの「送信取り消し機能」を最大時間(30秒)に設定しておくのも有効な対策です。
基本の型を覚えたら、次は具体的な場面での応用です。少しの工夫で、相手との認識のズレを防ぎ、スムーズなやり取りが実現できます。
口頭での指示は、聞き漏らしや解釈の違いが起こりがちです。指示を受けたら、必ずチャットやメールで内容を要約して送り、「受信力」を高めましょう。この一手間が、後々の大きな手戻りを防ぎます。
件名:【ご確認】先ほどの〇〇の件について
本文:
〇〇さん
お疲れ様です。〇〇です。
先ほどご指示いただいた件について、以下の認識で合っておりますでしょうか。
・What(何を):〇〇の資料作成
・Why(なぜ):来週の定例会議で使用するため
・When(いつまでに):明日の17時まで
・Who(誰が):私が担当
・Where(どこで):共有フォルダの〇〇に保存
・How(どのように):昨年のフォーマットを流用して作成
認識に相違がございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
「どこまで進んでいるかわからない」と上司を不安にさせないために、こまめな進捗報告が重要です。しかし、頻繁すぎても相手の時間を奪ってしまいます。そこで有効なのが「2・5・8の法則」です。作業全体の2割、5割、8割の段階で報告するルールを決めておくと、お互いに安心できます。
「お疲れ様です。〇〇の資料作成の件、全体の5割ほど完了しました。現時点でのドラフトを共有フォルダに置きましたので、方向性に問題ないか、お手すきの際にご確認いただけますでしょうか。」
ミスをしてしまった時は、迅速な謝罪が不可欠です。しかし、ただ謝るだけでは不十分です。大切なのは、「謝罪+事実関係+今後の対策」をセットで伝えること。これにより、誠実な姿勢と問題解決能力を示すことができ、かえって信頼を得るきっかけにもなり得ます。
件名:【お詫び】〇〇の誤送信について(自分の名前)
本文:
〇〇部長
大変申し訳ございません。
本日14時頃、私が送信したメールの宛先に誤りがございました。(謝罪と事実)
原因は、送信前の宛先確認を怠ったことです。(原因)
今後は、送信前に必ず「送信前チェックリスト」を用いて指差し確認を徹底いたします。(具体的な再発防止策)
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
テクニックを身につけても、心が疲弊してしまっては元も子もありません。最後に、自分自身を守り、長く働き続けるための心構えをお伝えします。
特に真面目な方ほど、100%完璧なコミュニケーションを目指してしまいがちです。しかし、仕事の目的は「完璧なメールを書くこと」ではなく、「業務を円滑に進めること」です。社内の気軽なやり取りであれば、多少の粗さよりもスピードが重視されることもあります。「6割の完成度で、まずは投げてみる」という意識を持つことで、心が軽くなります。
現代には、あなたの苦手さを補ってくれる便利なツールがたくさんあります。
また、「口頭での指示は、後からチャットでも送ってください」とお願いするなど、働きやすい環境を自ら作ることも大切です。これは「わがまま」ではなく、ミスなく業務を遂行するための合理的な配慮です。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも有効な選択肢です。就労移行支援事業所では、障害特性に応じたコミュニケーション訓練やビジネスマナー講座、自己理解を深めるプログラムなどを提供しています。同じ悩みを持つ仲間と出会えたり、専門の支援員が職場との間に入って調整してくれたりすることもあります。自分に合った働き方を見つけるための、心強いパートナーとなるでしょう。
メールやチャットでのコミュニケーションに苦手意識を持つことは、決して特別なことではありません。その背景には、あなたの持つ繊細さや真面目さ、そして特性があります。
大切なのは、根性論で乗り越えようとするのではなく、具体的な「スキル」として対処法を学ぶことです。今回ご紹介した「基本の型」や「実践テクニック」を一つでも試してみてください。小さな成功体験を積み重ねることで、自信がつき、コミュニケーションへの不安は着実に和らいでいきます。
あなたらしい働き方で、無理なく長くキャリアを築いていくことを、心から応援しています。
