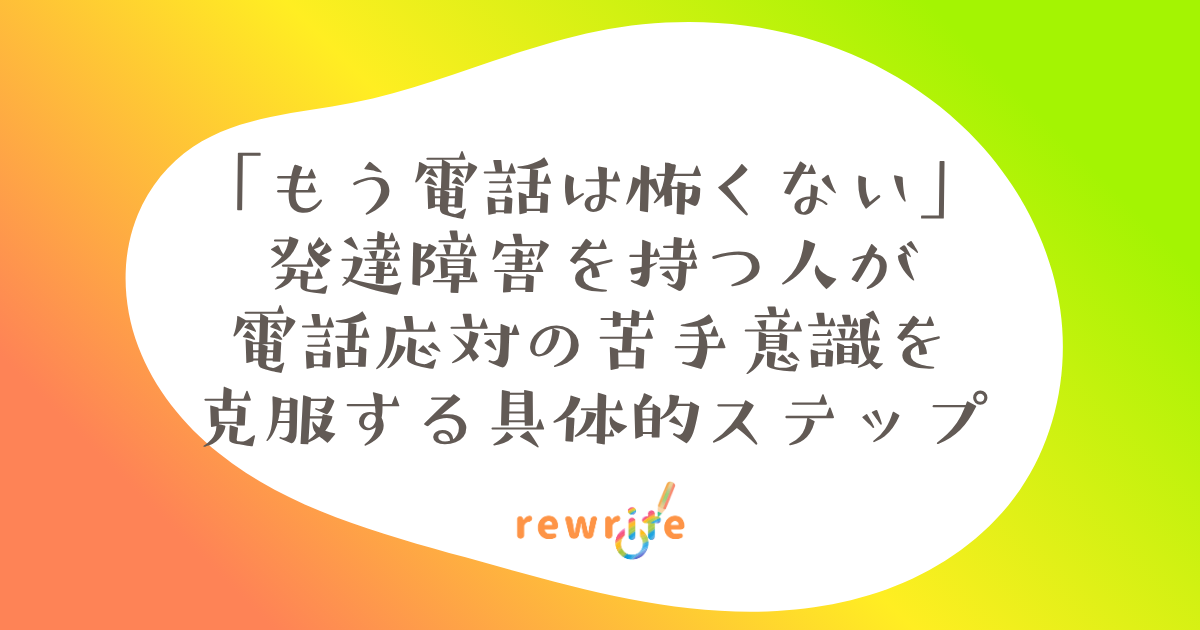
「会社の電話が鳴るたびに、心臓がドキッとする」「相手の言っていることが聞き取れず、頭が真っ白になる」——。このような悩みを抱えていませんか?
特にADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害の特性を持つ方にとって、電話応対は非常にストレスの大きい業務の一つです。過去の失敗経験から自信を失い、仕事そのものがつらくなってしまうことも少なくありません。
しかし、電話応対の苦手意識は、正しい知識と工夫によって克服することが可能です。この記事では、発達障害の特性を踏まえながら、電話応対の不安を軽減し、自信を持って対応できるようになるための具体的なステップを、準備から実践、そして環境調整まで網羅的に解説します。
まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)
まず、なぜ電話応対がこれほどまでに難しく感じるのか、その原因を理解することが克服への第一歩です。発達障害の特性と電話業務の性質が、いくつかの点でミスマッチを起こしていることが考えられます。
電話応対は、一見シンプルなようで、実は高度なマルチタスク業務です。「相手の話を聞く」「内容を理解する」「要点をメモする」「適切な返答を考える」「PCで情報を検索する」といった複数の作業を、ほぼ同時に、かつリアルタイムで処理する必要があります。
ADHDの特性の一つに、情報を一時的に記憶し処理するワーキングメモリの弱さがあります。そのため、次々と入ってくる情報を整理しきれず、頭が混乱してしまったり、聞いた内容をすぐに忘れてしまったりすることが起こりやすいのです。このマルチタスクがADHDを持つ人にとって電話応対を困難にする大きな要因であると指摘されることがあります。
発達障害の特性として、聴覚情報の処理が苦手であったり、感覚が過敏であったりする場合があります。例えば、以下のような困難を感じることがあります。
顔が見えない電話では、表情や口の動きといった視覚情報で聞き取りを補うことができないため、聴覚情報だけに頼らざるを得ず、困難さが一層増してしまいます。
ASDの特性を持つ方は、見通しが立たない状況や、決まった手順から外れることに強い不安を感じる傾向があります。電話はいつ、誰から、どんな内容でかかってくるか予測ができません。この「予測不能性」が、大きなストレス源となります。
「マニュアルにない質問をされたらどうしよう」「想定外のトラブルだったら対応できないかもしれない」といった不安が常に頭をよぎり、電話が鳴る前から緊張状態になってしまうのです。この予測不能性への対応策として「パターン化」の重要性が述べられています。
さらに、過去に電話応対で叱責されたり、大きなミスをしたりした経験があると、それがトラウマとなり、「電話恐怖症」ともいえる状態に陥ってしまうこともあります。
原因がわかったら、次はいよいよ対策です。いきなり電話に出るのではなく、事前の「準備」を徹底することが、不安を軽減し、成功体験を積むための鍵となります。
予測不能な状況が苦手なら、できる限り「パターン化」してしまいましょう。会社の既存マニュアルを参考にするのも良いですが、最も効果的なのは、自分にとって分かりやすい「専用マニュアル」を作成することです。
このマニュアルを手元に置いておくだけで、「これを見れば大丈夫」というお守りのような役割を果たしてくれます。
ワーキングメモリへの負荷を減らすため、情報を頭の中だけで処理しようとせず、積極的に外部のツールに頼りましょう。その最たるものがメモです。真っ白な紙にメモを取るのが苦手な場合は、あらかじめ項目を印刷した「電話メモ専用フォーマット」を用意するのが非常に有効です。
事前に「社名、担当者名、電話番号、用件」の4項目を紙に書いておくことで、聞き出すべきポイントが明確になり、プレッシャーが軽減されたとの声もあります。これに「受付日時」「受付者名」「折り返し要否」などを加えたフォーマットを作成し、常に電話の横に複数枚用意しておきましょう。これにより、メモを取る行為自体に集中しやすくなります。
マニュアルやメモ帳が準備できたら、次は実践練習です。いきなり本番に臨むのではなく、信頼できる上司や同僚、あるいは就労移行支援事業所の支援員などに協力してもらい、ロールプレイング(模擬練習)を繰り返しましょう。
練習の目的は、作成したマニュアルやフレーズを、考えなくても口から出てくるレベルまで体に染み込ませることです。何度も声に出して練習することで、受け答えがスムーズになり、「練習でできたのだから本番も大丈夫」という自信につながります。
まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)
準備が整ったら、いよいよ実践です。応対中にパニックになりそうになったときに思い出したい、具体的なコツをいくつか紹介します。
まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)
個人の努力や工夫だけで対応するのが難しい場合、職場環境を調整してもらうことも検討しましょう。障害者雇用で働いている場合、事業主には「合理的配慮」を提供する義務があります。
合理的配慮とは、障害のある人が他の従業員と平等に働けるように、職場が提供する調整や変更のことです。例えば、「電話応対業務を免除または軽減してもらう」「かかってきた電話は一次受けだけ行い、詳細は他の人に引き継ぐ」「内線電話のみ対応する」といった配慮を求めることができます。
配慮を求めるためには、まず自分の障害特性や、それによってどのような困難が生じているのかを上司や人事担当者に具体的に伝えることが大切です。勇気がいることかもしれませんが、無理なく長く働き続けるためには非常に重要なステップです。
また、これから就職・転職を考える場合は、求人票で「電話応対なし」と明記されている職種(データ入力、プログラマー、一部の軽作業など)を選ぶのも有効な戦略です。
電話応対の苦手意識は、多くの発達障害当事者が抱える共通の悩みです。しかし、それはあなたの能力が低いからではありません。特性と業務内容のミスマッチが原因であり、適切な「準備」「工夫」「環境調整」によって、その壁は乗り越えることができます。
今回ご紹介したステップを、まずは一つでも試してみてください。
完璧を目指す必要はありません。昨日より少しでも落ち着いて対応できたなら、それは大きな一歩です。小さな成功体験が、やがて「電話はもう怖くない」という確かな自信に変わっていくはずです。
まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)
