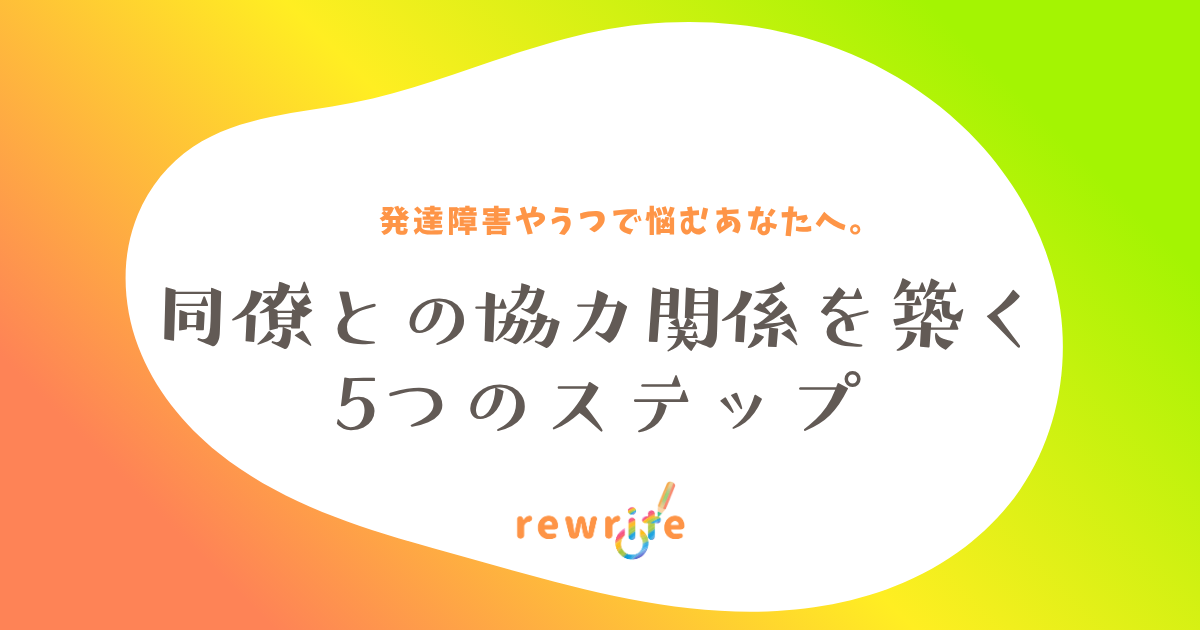
この記事では、「友達になる」ことではなく、あくまで「仕事上のパートナー」として、お互いが安心して業務を進められる「協力関係」を築くための、具体的で実践的な5つのステップをご紹介します。一つひとつ、あなたに合った方法で試してみてください。
他人と協力関係を築くための第一歩は、まず自分自身を深く理解することです。特に発達障害の特性を持つ方にとって、これは最も重要な土台となります。なぜなら、自分の得意・不得意、ストレスを感じる状況などを客観的に把握できていなければ、他人に協力を求めることも、誤解を防ぐことも難しいからです。
感情的に「自分はダメだ」と責めるのではなく、事実として自分の特性をリストアップしてみましょう。
上記の分析をもとに、「自分の取扱説明書」を作成します。これは、他者に自分の特性を理解してもらい、どうすれば円滑に仕事ができるかを伝えるためのツールです。目的は「配慮を求める」ことだけでなく、「こうすれば、私は最大限のパフォーマンスを発揮できます」と提示し、チームへの貢献意欲を示すことにあります。
【取扱説明書の記載例】
■得意な業務:
・マニュアルに沿った定型作業
・データ入力や校正などの緻密な作業■パフォーマンスを最大化するために:
・ご指示は、口頭ではなくチャットやメールなど、テキストでいただけると助かります。(聞き漏らしや解釈の間違いを防ぐため)
・集中している時はヘッドホンを着用しています。急ぎでないご用件の場合は、メッセージを残していただけると幸いです。
・複数の業務が重なった際は、優先順位をご相談させてください。
この「取扱説明書」は、次のステップである「情報開示」の際に、あなたの強力な味方となります。
自分の特性を職場に伝えるべきか(クローズかオープンか)は、非常にデリケートで悩ましい問題です。ここでは、すべてを話すか話さないかの二者択一ではなく、より戦略的な「情報開示」の方法を考えます。
必ずしも「私にはADHDがあります」と診断名を伝える必要はありません。相手によっては、偏見や誤解を招くリスクもゼロではないからです。重要なのは、「あなたが働く上で、具体的に何が必要か」を伝えることです。ステップ1で作成した「取扱説明書」がここで活きてきます。
診断名を伏せて、以下のように伝える方法があります。
「恐れ入りますが、私は口頭での指示を一度に記憶するのが少し苦手でして。後で確認できるよう、要点をチャットで送っていただくことは可能でしょうか?」
このように、診断名ではなく「苦手なこと」と「具体的な代替案(してほしいこと)」をセットで伝えることで、相手も協力しやすくなります。
障害者雇用促進法では、事業主に対して「合理的配慮」の提供が義務付けられています。これは、障害のある人が他の従業員と平等に働けるよう、個々の状況に応じて必要な調整や変更を行うことです。もし診断を受けており、オープン就労を選択する場合は、この権利を正当に活用できます。
伝える相手は、まず直属の上司や人事部の担当者など、信頼でき、かつ権限のある人から始めると良いでしょう。伝える際は、感情的にならず、あくまで「業務を円滑に進め、チームに貢献するため」という前向きな姿勢で相談することが大切です。あなたの真摯な態度は、きっと相手に伝わります。
日本の組織文化で重視される「報告・連絡・相談(報連相)」は、発達障害の特性やうつの症状によって、特に難しく感じられることがあります。
しかし、報連相は「同僚との信頼関係の生命線」です。自分に合った方法で仕組み化し、徹底することが重要です。無理に「空気を読んで」行う必要はありません。
「相談=自分の無能さを示すこと」ではありません。「相談=問題が大きくなる前に対処する、責任感のある行動」です。上司や先輩に、あらかじめ相談のルールを確認しておくのも有効です。
「〇〇さん、業務で行き詰まった際にご相談したいのですが、どのようにお声がけするのがご都合よろしいでしょうか?チャットでアポイントを取る形が良いですか?」
このように事前に確認しておくことで、心理的なハードルがぐっと下がります。
協力関係は、一方的なものでは成り立ちません。あなたが周囲に配慮を求めるのと同じように、あなたも周囲に対して関心と感謝を示すことが大切です。しかし、ASDの特性で他者への関心が薄い、あるいはうつの症状で他人の良い面に目が向きにくい、と感じるかもしれません。ここでも「具体的」であることが鍵となります。
漠然と「ありがとうございます」と言うだけでなく、「何に対して感謝しているのか」を具体的に伝えましょう。
(悪い例)「ありがとうございます」
(良い例)「〇〇さん、先ほど教えていただいたショートカットキー、すごく便利です!作業が速くなりました。ありがとうございます!」
(良い例)「△△の資料、共有いただき助かりました。おかげで今日の会議の準備が間に合いました。本当にありがとうございます。」
具体的な感謝は、相手に「自分の行動が役に立った」という実感を与え、次の協力へのモチベーションを高めます。
無理にプライベートな雑談をする必要はありません。相手の「仕事」に関心を示しましょう。これは、相手を尊重し、チームの一員として認めているというサインになります。
「先日の〇〇さんのプレゼン、データがすごく分かりやすかったです。どうやって分析されたんですか?」
「そのツール、便利そうですね。もしよろしければ、後で少し使い方を教えていただけませんか?」
仕事に関することであれば、会話の目的が明確なため、コミュニケーションが苦手な方でも比較的取り組みやすいはずです。
孤立感を抱きやすい方は、「自分 vs 仕事」という構図に陥りがちです。しかし、会社はチームで成果を出す場所です。視点を「私」から「私たち(チーム)」へと切り替えることで、協力関係は格段に築きやすくなります。
上司やリーダーに、「この仕事は、プロジェクト全体のどの部分にあたり、どのような役割を果たしますか?」と確認してみましょう。自分の仕事の「意味」や「貢献度」が分かると、モチベーションが向上するだけでなく、他のメンバーの仕事との関連性も見えてきます。
会議や相談の場で、「私はこう思う」だけでなく、「私たちはどうすればこの課題を解決できるでしょうか?」「私たちのチームの目標達成のためには、何が必要ですか?」といったように、「私たち」を主語に使うことを意識してみましょう。これにより、あなたは単なる作業者ではなく、チームの目標達成を共に考える当事者であるという姿勢を示すことができます。
ミスをしてしまった時、過度に自分を責めてしまう傾向はありませんか。もちろん反省は必要ですが、それを「チームの課題」として捉え直すことも大切です。
「申し訳ありません。私の確認不足でミスがありました。今後、チームとして同様のミスを防ぐために、ダブルチェックの仕組みを導入するのはいかがでしょうか?」
このように提案することで、個人の失敗をチーム全体の改善に繋げることができます。これは、あなたが責任感を持って仕事に取り組んでいる証拠であり、周囲からの信頼を高める行動です。
同僚との協力関係を築くための5つのステップをご紹介しました。
これらのステップは、あなたの特性を無理に変えるためのものではありません。むしろ、あなたの特性を活かしながら、社会の中で無理なく働くための「技術」や「戦略」です。
すぐにすべてを完璧にこなす必要はありません。まずは「これならできそう」と思えるものから、一つ試してみてください。小さな成功体験を積み重ねることが、自信となり、次のステップへの力となります。
無理なく、あなたらしく働ける場所は必ずあります。焦らず、一歩ずつ、あなたに合った働き方を見つけていきましょう。
