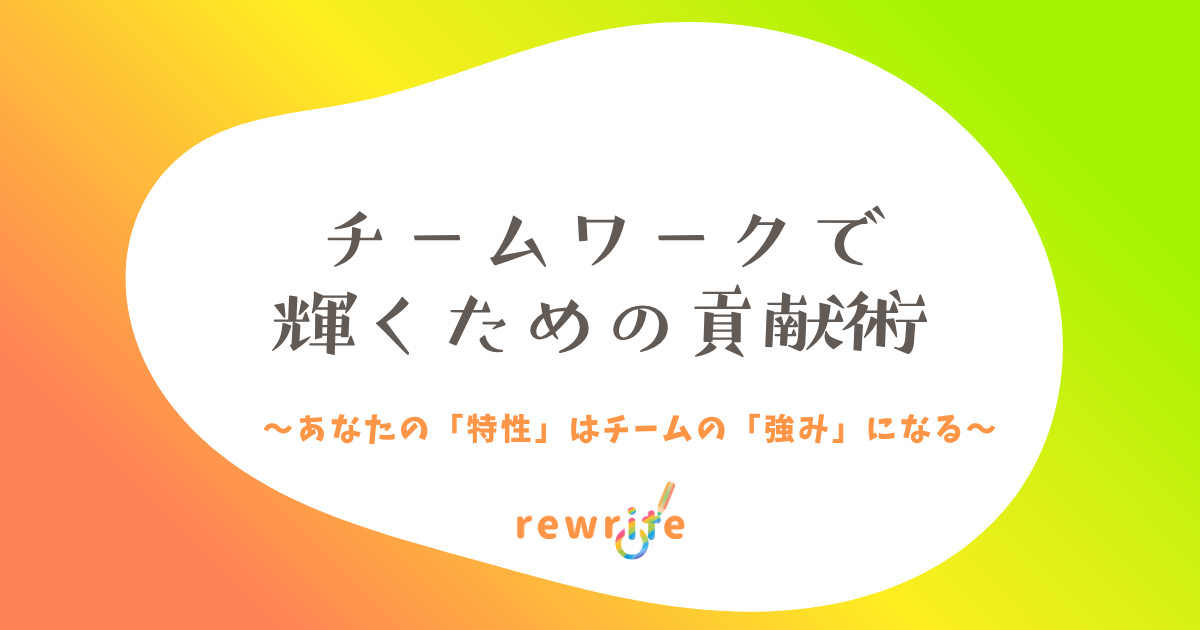
チームへの貢献を考える第一歩は、自分自身が「欠点」だと思い込んでいる特性を、ポジティブな側面から見つめ直すことです。多くの発達障害の特性は、環境や役割が合致すれば、非常に高いパフォーマンスを発揮する「強み」に変わります。
以下は、一般的に「弱み」とされがちな特性と、それがチームワークにおいてどのように「強み」として機能しうるかを示したものです。
・過集中
(ADHDなど) 時間を忘れて没頭し、周りが見えなくなる。
┗高い集中力と生産性
特定のタスク(データ分析、プログラミング、執筆など)において、驚異的な集中力を発揮し、質の高い成果を短時間で生み出せます。
・こだわりが強い
(ASDなど) ルールや手順、自分のやり方に固執する。
┗品質管理能力と正確性
マニュアル遵守や細部のチェック、規則性の発見が得意。製品やサービスの品質を担保する「最後の砦」として活躍できます。
・衝動性・多動性
(ADHDなど) 思いついたらすぐ行動する。じっとしていられない。
┗豊富なアイデアと行動力
会議で行き詰まった際に新しい視点を提供したり、停滞しているプロジェクトを動かす起爆剤になったりします。
・シングルタスクが得意
(ASDなど) 複数のことを同時に進めるのが苦手。
┗一つの業務への深い没入力
マルチタスクが求められない専門的な業務において、他の誰よりも深く掘り下げ、専門性を高めることができます。
・独自の視点・感覚
「空気が読めない」と言われることがある。
┗既成概念を打ち破る発想力
チームの誰もが気づかなかった問題点や、斬新な解決策を発見するきっかけを作ります。イノベーションの源泉となり得ます。
自分の特性を「強み」として認識できたら、次はそれをチームの中で具体的にどう活かしていくかを考えます。ここでは、明日からでも実践できる5つの貢献方法をご紹介します。
自分の「強み」が活かせる仕事に、自ら手を挙げてみましょう。「苦手なことを克服する」よりも「得意なことで貢献する」方が、あなたにとってもチームにとっても遥かに生産的です。
【ケーススタディ】
ASD傾向のあるAさんは、口頭でのコミュニケーションに苦手意識がありましたが、資料の細かなミスを見つけるのが非常に得意でした。チームが作成した提案書の最終確認を毎回担当するようになり、「Aさんが見てくれれば安心だ」と絶大な信頼を得るように。彼の貢献により、チームの成果物の品質は格段に向上しました。
発達障害の特性上、口頭でのリアルタイムな「報・連・相」が苦手な場合があります。タイミングを逃したり、何を伝えればよいか分からなくなったりすることも。無理に周りに合わせようとせず、自分に合った方法を確立し、それをチームに理解してもらうことが重要です。
「報・連・相が苦手です」と伝えるだけでなく、「その代わりに、このような方法で確実に共有します」と代替案をセットで提示することで、周囲も安心してあなたに仕事を任せられます。
あなたが「当たり前」や「非効率だ」と感じることは、他のメンバーが気づいていない重要な視点かもしれません。しかし、それを単なる「批判」や「問題指摘」として伝えると、角が立ってしまうことがあります。
そこで、「〇〇という課題があると思います。解決策として、△△という方法はいかがでしょうか?」というように、必ず「課題」と「改善提案」をセットにして伝えることを意識しましょう。これにより、あなたのユニークな視点は、チームを前進させるための建設的な意見として受け入れられやすくなります。
多くの情報が飛び交う会議は、発達障害を持つ方にとって大きなストレスとなり得ます。情報処理が追いつかなかったり、発言のタイミングが掴めなかったりするためです。そんな時は、会議の中で特定の「役割」を担うことで、混乱を防ぎ、貢献実感を得ることができます。
事前にファシリテーターや上司に「今回の会議では、議事録を担当させていただけますか?」と相談してみましょう。
チームワークは、タスクの連携だけでなく、感情的なつながりも大切です。社会的なコミュニケーションが苦手だと感じていても、意識的にできることがあります。それは、「感謝」と「ポジティブなフィードバック」を言葉にして伝えることです。
たとえ短い言葉でも、具体的に伝えることで、相手は「自分の行動を見てくれている」と感じ、チーム内の心理的安全性が高まります。これは練習によって上達できるスキルであり、人間関係を円滑にする強力なツールです。
あなたの強みを最大限に活かすには、それを受け入れ、評価してくれる環境を選ぶことが不可欠です。次の就職で失敗しないために、以下の3つの準備を徹底しましょう。
自分自身を客観的に理解し、他者に分かりやすく伝えるための「取扱説明書(トリセツ)」を作成しましょう。これは、就職活動の軸を定め、入社後に適切な配慮を求める上で非常に役立ちます。
この「トリセツ」は、まず自分自身が働きやすくなるための羅針盤です。そして、信頼できる上司や人事ができた際に、開示することで、より良い職場環境を共に作っていくための土台となります。
求人票の表面的な情報だけでなく、その企業が本当に多様な人材を活かそうとしているかを見極めることが重要です。
就職活動や、就職後の定着に不安がある場合、一人で抱え込む必要はありません。専門的な知識と経験を持つ支援機関を積極的に活用しましょう。
これらの機関は、あなたの「トリセツ」作りを手伝い、あなたに合った企業を見つけ、入社後もあなたが安定して働き続けられるようにサポートしてくれる心強い味方です。
発達障害の特性によって社会になじめず、辛い経験をしてきたかもしれません。しかし、それはあなたの価値が低いからではありません。ただ、あなたの持つユニークな「特性」と、それを活かせる「環境」が、まだ出会っていなかっただけです。
この記事で紹介したように、
ができれば、あなたは「足手まとい」などではなく、チームにとって「不可欠な存在」になることができます。
あなたの独自の視点や、特定の分野への深い集中力は、多くのチームが求めているものです。自信を持って、あなただけの貢献の形を見つけてください。次の一歩が、あなたにとって無理なく、長く、そして輝ける場所へとつながることを心から願っています。
