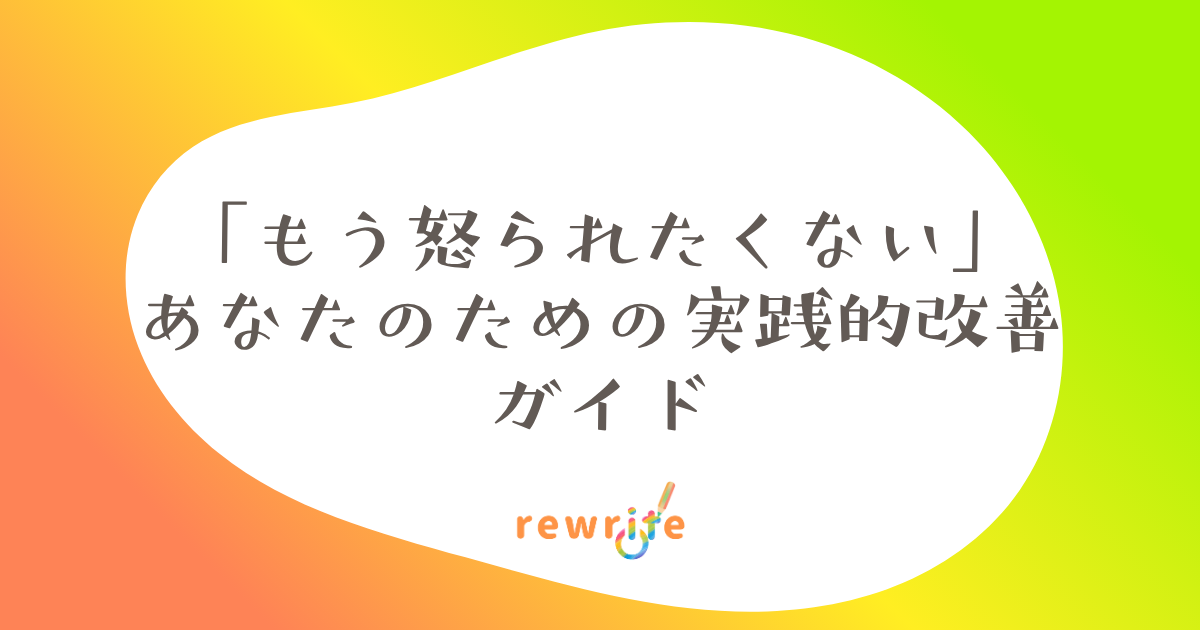
まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)
報連相ができないのは、あなたのやる気や能力が低いからではありません。多くの場合、脳の特性や過去の経験が複雑に絡み合っています。原因を正しく理解することが、自分に合った対策を見つける第一歩です。
発達障害の特性は、報連相の各プロセスで特有の困難を生じさせることがあります。
うつ病や不安障害も、報連相の大きな障壁となります。気力や体力の問題だけでなく、認知の歪みが大きく影響します。
過去に報連相を試みた結果、厳しく叱責されたり、馬鹿にされたりした経験は、心に深い傷を残します。これが「報連相恐怖症」とも言える状態を引き起こします。
負のスパイラル
この悪循環に陥ると、報連相は「自分の身を守るためのスキル」ではなく、「自分を危険に晒す行為」として脳にインプットされてしまいます。この状態から抜け出すには、小さな成功体験を積み重ね、安全なコミュニケーションを再学習する必要があります。
まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)
報連相はセンスではなく、練習で身につく「技術」です。ここでは、誰でも実践できるよう、報告・連絡・相談をそれぞれ分解し、具体的な「型」とツール活用法を解説します。
報告の目的は「上司や関係者に、業務の進捗や結果を正確に伝え、次の判断を仰ぐこと」です。難しく考えず、以下の型を使いましょう。
「適時」という曖昧な言葉に惑わされないよう、自分の中で報告のタイミングをルール化します。
★実践ポイント:スマートフォンのリマインダー機能で「11:30 進捗報告」「17:00 終業報告」など、定時アラームを設定するのが非常に効果的です。
口頭での報告が苦手な人は、まずメモ帳やチャットの下書きに以下のテンプレートで内容を整理してから話しましょう。
基本の報告テンプレート①結論(Point):「〇〇の件、完了しました/問題が発生しました」
②経緯・理由(Reason):「ご指示の通り、AとBのデータを用いて分析しました」
③現状・具体例(Example):「結果は別紙の通りです。特に、項目Cに想定外の数値が出ています」
④今後の対応・相談(Point):「このまま進めてよろしいでしょうか?/対応についてご相談させてください」
最初はすべてを完璧に伝えようとせず、「①結論」だけでも先に言うことを意識してください。「〇〇の件でご報告です」と切り出すだけで、相手は聞く準備ができます。
連絡は「事実情報を、関係者と共有すること」です。自分の意見や感情は含めず、客観的な事実を伝えるのがポイントです。
「誰に言えばいいんだっけ?」と迷う時間をなくすため、プロジェクトや業務ごとに「連絡すべき人リスト」を事前に作成しておきましょう。
このリストをデスクに貼っておく、またはテキストファイルで保存しておくだけで、いざという時に迷いません。
連絡手段は、緊急度や内容によって使い分けるのが理想です。職場のルールを確認しましょう。
★実践ポイント:判断に迷ったら、「記録が残るチャットやメール」を基本にしましょう。「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、後から自分でも確認できます。
相談は、多くの人が最も苦手とするところです。しかし、相談は「無能の証明」ではなく、「チームとしてのリスク管理」です。一人で抱え込んで大きな問題にする方が、よほどチームに迷惑をかけます。このマインドセットが重要です。
「もう少し自分で考えれば…」と無限に悩んでしまうのを防ぐため、時間で区切るルールを設けます。
「一つの問題で15分以上調べても解決策が見えない場合は、誰かに相談する」
この「15分ルール」は、Googleなど多くの企業でも採用されている効率的な手法です。時間を区切ることで、悩むことから行動へ切り替えるきっかけになります。
「わかりません、教えてください」と丸投げすると、相手も困ってしまいます。相談する前に、少しだけ準備をしましょう。
良い相談の構成①現状の共有:「〇〇の作業をしているのですが、△△の部分でエラーが出てしまいました」
②試したこと:「マニュアルのP.5の方法と、過去の事例にあったBの方法を試してみましたが、解決しませんでした」
③自分の考え・仮説:「原因はCではないかと考えているのですが、確信が持てません。もしかしたらDという可能性もありますか?」
④質問:「この状況の場合、次に何を試すべきでしょうか?/〇〇さんのご意見をお聞かせいただけますか?」
ここまで準備すれば、相手はあなたの状況をすぐに理解でき、的確なアドバイスをしやすくなります。「自分で考えているな」という姿勢が伝わり、信頼関係の構築にも繋がります。
まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)
自分を変える努力と同時に、環境を調整することも、長く働くためには不可欠です。少しの工夫で、働きやすさは劇的に改善します。
もし可能であれば、信頼できる上司や同僚に、自分の特性や苦手なことを正直に伝え、協力を仰ぎましょう。これを「セルフ・アドボカシー(自己権利擁護)」と言います。
診断名を伝える必要はありません。「どうすれば、より良く働けるか」という具体的な要望として伝えるのがコツです。
伝え方の例
このように伝えることで、相手もどう配慮すれば良いかが明確になり、お互いのストレスを減らすことができます。
現代には、私たちの苦手な部分を補ってくれる便利なツールがたくさんあります。積極的に活用しましょう。
これから就職・転職を考えるなら、自分の特性に合った環境を選ぶことが最も重要です。
面接の際に、「チーム内の主なコミュニケーションツールは何ですか?」「タスク管理はどのように行っていますか?」といった質問をすることで、その会社の働き方を具体的に知ることができます。
報連相は、一度にすべてを完璧にこなそうとすると、プレッシャーで押しつぶされてしまいます。大切なのは、完璧を目指すのではなく、昨日より少しでも改善しようとすることです。
この記事で紹介した中から、まずは一つだけ、一番簡単そうだと思うものを選んで試してみてください。
その小さな一歩が、あなたの自信となり、次のステップへと繋がっていきます。報連相は、あなたを苦しめるものではなく、あなた自身とチームを守るための強力な武器になり得ます。
あなたは一人ではありません。自分に合った方法を見つけ、工夫を重ねることで、無理なく、あなたらしく長く働ける道は必ず見つかります。
まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)
