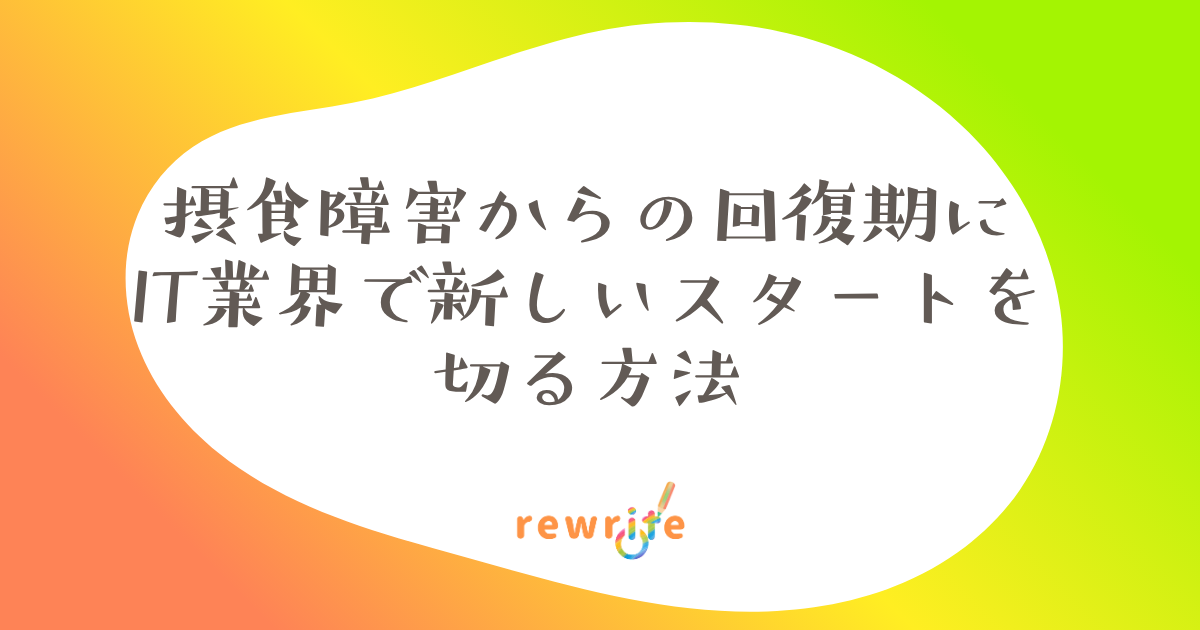不安を希望に変える、あなたのための一歩
摂食障害という長いトンネルを抜け、少しずつ光が見えてきた回復期。心と体が社会復帰に向けて準備を始める一方で、「また、あの頃のように働けるだろうか」「周りに迷惑をかけてしまわないか」「そもそも、今の私に何ができるんだろう」といった、漠然とした不安が押し寄せてくることもあるかもしれません。
完璧でなければならないというプレッシャー。体調の波に対する焦り。周囲の視線への過剰な意識。そうした経験が、新しい一歩を踏み出す勇気をくじいてしまうのは、決してあなただけではありません。
完璧じゃなくても大丈夫。あなたのペースで、あなたらしく輝ける新しい道は、確かに存在します。
私たちは、静岡県浜松市でIT分野に特化した就労移行支援事業所「リライトキャンパス浜松駅南」を運営する株式会社rewriteです。多くの回復期にある方々の社会復帰をサポートしてきた専門的なスタッフの知見等から、なぜ「IT業界」が摂食障害からの回復期にあるあなたにとって、有力な選択肢となりうるのかを解き明かしていきます。
この記事があなたに提供する価値
- なぜIT業界が回復期にあるあなたにとって有力な選択肢なのか、その具体的な理由を論理的に解説します。
- 体調と治療を最優先にしながら、無理なくITスキルを身につけ、就職に至るまでの具体的なロードマップを提示します。
- 就職活動や職場で直面しがちな課題(食事、体調管理、人間関係)への対処法と、必要なサポートを企業に上手に伝える方法を詳しく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの胸の中にある漠然とした不安が、「私にもできるかもしれない」という具体的な希望と、次の一歩を踏み出すための確かな道筋に変わっていることをお約束します。なぜIT業界?摂食障害からの回復期と驚くほど高い親和性
「働くこと」への不安は、多くの場合、過去の辛い経験に基づいています。まずは、その困難を具体的に見つめ直すことから始めましょう。そして、それらの困難が、現代のIT業界が持つユニークな特性によって、いかに解消されうるのかを論理的に探っていきます。これは、あなたがIT業界を「自分ごと」として捉え、読み進めるための最も重要なパートです。
回復期に直面する「働く上での困難」の再確認
摂食障害からの回復期にある方が仕事をする上で困難を感じる点は、決して気のせいではありません。日本摂食障害協会が実施した調査報告書では、当事者が職場で直面する具体的な困難が浮き彫りにされています。多くの人が共感するであろう、代表的な困難は以下の通りです。
- 食事に関するプレッシャー:「必ず全員同じ時間、同じ空間で昼休憩をとるので緊張する」「職場内外の付き合いで食事会が多く、断れない」「おやつを配られ、食べないと気まずい雰囲気気になる」といった、食にまつわる避けがたい状況。
- 心身の不安定さ:体力や気分の波が激しく、一定のパフォーマンスを維持することへの困難。過食衝動による集中力の低下。
- 対人関係の緊張:「どうして食べないの?」といった無理解な質問や、体型への言及。周囲の視線が気になり、常に緊張を強いられる環境。
- 完璧主義と自己肯定感の問題:ミスを過度に恐れ、自分を追い詰めてしまう傾向。病気のことを隠している罪悪感や、仕事上の空白期間に対する説明の難しさ。
これらの困難は、従来の画一的な働き方を前提とした職場環境では、個人の努力だけでは乗り越えがたい大きな壁となります。しかし、働き方が大きく変化しているIT業界には、これらの壁を乗り越えるための「鍵」がいくつも存在しているのです。
IT業界の特性がこれらの困難をどう乗り越える「鍵」になるか
IT業界の柔軟な働き方や評価文化は、前述した困難を軽減し、あなたの特性を「強み」に変える可能性を秘めています。
1. 柔軟な働き方と「食の自由」
IT業界、特にソフトウェア開発やWeb制作などの分野では、リモートワークやフレックスタイム制が他の業界に比べて格段に普及しています。これは、回復期のあなたにとって計り知れないメリットをもたらします。
テレワークの普及は、通勤ストレスの軽減だけでなく、「孤独感」「生活リズムの乱れ」「コミュニケーション不足」といった新たな課題も生んでいますが、適切に活用すれば、個人の裁量で仕事を進めやすい環境を提供します。
- 自分のペースで食事と休憩:自宅でのリモートワークであれば、決まった時間に同僚と一斉に昼食をとるプレッシャーから解放されます。自分の体調に合わせて、好きな時間に、好きな場所で、安心して食事をとることが可能です。
- 「一人で昼食」が自然な文化:オフィス勤務であっても、イヤホンで音楽を聴きながら自席で黙々と作業するエンジニアは珍しくありません。「一人で昼食を食べていると『なんで一人なの?』と聞かれて憂鬱」といった悩みは、IT業界では起こりにくいと言えるでしょう。
- 不要な飲み会からの解放:プロジェクトの打ち上げなどを除き、業務外の付き合いが比較的少ない文化の企業も多く、特にリモート中心の働き方では、食事会への参加プレッシャーは大幅に軽減されます。
2. 業務特性と心身の波への対応
IT業界の多くの職種は、タスクベースで仕事が進みます。これは、日々の体調や気分の波に対応しやすいという大きな利点があります。
- 明確なゴールと自分のペース:プログラミング、Webデザイン、データ入力、ライティングといった業務は、「この機能を実装する」「このページをデザインする」といったゴールが明確です。体調が良い時に集中して進め、少し辛い時はペースを落とすといった調整が、個人の裁量で行いやすいのです。
- テキスト中心のコミュニケーション:タスクを細分化し、具体的で明確な指示をすることが推奨される文化は、対人緊張を和らげます。多くの企業でSlackやTeamsといったチャットツールが主要なコミュニケーション手段となっており、対面での会話が苦手な人でも、自分のタイミングで考えをまとめて発信できます。
3. 評価基準と自己肯定感の醸成
摂食障害の背景には、しばしば完璧主義や低い自己肯定感が存在します。IT業界のスキルベースの評価文化は、こうした課題と向き合い、新たな自信を育む上で非常に有効です。
- 成果が「見える」ことの力:あなたが書いたコードが正しく動いた時、デザインしたWebサイトが完成した時、分析したデータから新たな知見が見つかった時。ITの仕事は、あなたの努力が具体的で目に見える「成果物」として現れます。この客観的な成果の積み重ねは、他人の評価に左右されない、確かな自己肯定感を育む土壌となります。
- 「完璧主義」が「強み」に変わる瞬間:コンピュータを動かす上では論理性が求められ、曖昧さは許されないため、完璧主義な性格が求められる面があります。細部へのこだわり、ロジックを突き詰める思考力、粘り強く問題解決に取り組む姿勢は、プログラミングやデバッグ、データ分析といった分野で非常に高く評価される「強み」となり得ます。
- 多様性を受け入れる文化(DE&I):近年、IT業界ではDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)の推進が活発です。多様な視点を持つチームがより良い製品を生み出すという考え方が浸透しつつあり、画一的でない、多様な背景を持つ人材が尊重される傾向にあります。これは、病気の経験を持つあなたが、その経験を隠すのではなく、一つの個性として受け入れられる環境を見つけやすいことを意味します。
注意点と次のステップへの橋渡し
もちろん、IT業界が誰にとっても「楽園」というわけではありません。その光と影を正しく理解することが、成功への第一歩です。
調査によれば、日本の労働者全体で「強い不安やストレスを感じている」人は82.2%にのぼり、特にIT業界は長時間労働や厳しい納期プレッシャー、テレワークによるコミュニケーション不足など、特有のストレス要因を抱えています。メンタルヘルス不調で休職・退職するケースも決して少なくありません。
だからこそ、重要なのは「どの業界か」だけでなく、「どのような企業で、どのようなサポートを受けながら働くか」です。業界の特性を最大限に活かし、リスクを最小限に抑えるためには、あなたに合った環境を慎重に選び、専門的なサポートを活用することが不可欠となります。
では、具体的にどのようなステップを踏めば、回復とキャリアを両立させながら、安心して働ける未来にたどり着けるのでしょうか。次のセクションでは、そのための具体的なロードマップを3つのステップに分けて詳しく解説します。
回復とキャリアを両立する、あなただけの3ステップ・ロードマップ
「IT業界が良いかもしれない」と感じても、何から手をつければいいのか分からなければ、不安は解消されません。ここでは、あなたが明日から具体的な行動を起こせるよう、回復期の心身の状態に寄り添った、現実的な3つのステップを提案します。
ステップ1:自己理解と準備フェーズ「心と体の土台を固め、進むべき道を探る」
このフェーズの目標は、焦ってスキル習得に飛びつくことではありません。まずは心と体の安定を最優先に、安全な航路図を描くための準備をすることです。
アクション項目:
- 主治医・カウンセラーとの作戦会議:あなたの最も信頼できる専門家である主治医やカウンセラーと、就労について具体的に相談しましょう。「働く」という目標を共有し、治療計画と両立できる働き方の条件を一緒に整理します。例えば、「週3日の半日勤務から始めたい」「通院日は確保したい」「リモートワーク中心の職場が望ましい」など、就労準備性における体調管理の観点から、あなたにとって無理のない条件を明確にすることが、最初の重要な一歩です。
- IT業界の職種リサーチ(探索):「IT 未経験 障害者雇用」「在宅 プログラマー」といったキーワードで、求人情報サイトを眺めてみましょう。この段階では応募する必要はありません。Webデザイナー、IT事務、ソフトウェアテスター、Webマーケティングアシスタントなど、世の中にどんな仕事があるのかを知るのが目的です。仕事内容を読んで、「これなら興味が持てるかも」「この作業は自分に向いていそう」と感じるものをいくつか見つけてみましょう。
- 自己分析と興味のマッチング(再発見):摂食障害の経験は、辛いものであったと同時に、あなたにユニークな強さをもたらしたかもしれません。例えば、食事や体重を細かく管理してきた経験は「データ分析力」や「緻密さ」に、完璧を求めて努力し続けた経験は「探求心」や「粘り強さ」に繋がっている可能性があります。リカバリーのプロセスで自己と向き合った経験は、深い「自己分析能力」を育んだかもしれません。これらの特性を「強み」として捉え直し、どの職種に活かせそうか考えてみることは、自信を取り戻すきっかけになります。
ステップ2:スキル習得フェーズ「自信を育む、小さな成功体験の積み重ね」
進むべき道の方向性が見えてきたら、次はいよいよスキルという名の「武器」を手に入れるフェーズです。ここでの目標は、完璧なスキルを身につけることではなく、無理のないペースで「できた!」という小さな成功体験を積み重ね、自信を育むことです。
アクション項目:
- 学習方法の選択:ITスキルを学ぶ方法は一つではありません。独学、オンラインスクール、公的な職業訓練、そして就労移行支援。それぞれのメリット・デメリットを理解し、今のあなたに最適な方法を選びましょう。
IT特化型就労移行支援の強み:特に回復期にある方にとって、IT特化型就労移行支援は非常に有力な選択肢です。プログラミングやWebデザイン等の専門スキル習得だけでなく、障害特性への深い理解に基づくストレスコントロールや自己理解のプログラム、安定した通所を支えるための体調管理サポート、時には昼食提供などの生活支援が一体となっている点が最大の強みです。一人で抱え込まず、専門家チームのサポートを受けながら学べる安心感は、何物にも代えがたいでしょう。
- 学習計画の立案(完璧を目指さない):「毎日8時間勉強する」といった無理な計画は禁物です。回復期には、調子の良い日もあれば、そうでない日もあります。大切なのは、継続すること。「まずは1日30分、Progateに触れてみる」「今週はHTMLで簡単な自己紹介ページを作る」など、達成可能な小さな目標を設定し、クリアしていく感覚を楽しみましょう。できなかった日があっても、自分を責めないこと。それも回復のプロセスの一部です。
- ポートフォリオの作成(最強の武器):学習したことの「証」として、簡単な作品を作りましょう。それは、自己紹介を載せた1ページのWebサイトかもしれませんし、架空のお店のバナー画像かもしれません。この「ポートフォリオ」は、あなたのスキルレベルを客観的に証明し、職務経歴書や面接で「私にはこれができます」と自信を持って示すための最強の武器になります。
ステップ3:就職活動と実践フェーズ「安心して働ける『居場所』を見つける」
スキルと自信という武器を手に入れたら、いよいよ実践の場、つまり「安心して働ける居場所」を見つけるフェーズです。ここでの目標は、内定を勝ち取ることだけではありません。あなたらしく、長く働き続けられる環境を見つけることです。
アクション項目:
- 企業選びの軸を定める:給与や業務内容だけでなく、「働きやすさ」という軸を大切にしましょう。企業の公式サイトや求人情報、採用ブログなどをチェックし、ダイバーシティ推進や障害者雇用に積極的か、EAP(従業員支援プログラム)のようなメンタルヘルスケア制度が導入されているか、などを確認します。企業の文化が、あなたの価値観と合うかどうかを見極めることが重要です。
- 応募書類の準備:履歴書や職務経歴書で、病気によるブランク期間をどう説明するか悩むかもしれません。しかし、これは「療養に専念し、自己と向き合いながら、新たなキャリアに向けてITスキルを習得した自己投資の期間」と前向きに表現することも可能です。そして、ステップ2で作成したポートフォリオのURLを記載し、言葉だけでなく「成果物」であなたのスキルと意欲を伝えましょう。
- 面接対策(一人で戦わない):面接は、企業があなたを選ぶ場であると同時に、あなたが企業を選ぶ場でもあります。自分の状態や必要な配慮について、誠実に、かつ的確に伝える準備が必要です。この時、就労移行支援事業所の支援員に面接に同席してもらうという選択肢は非常に有効です。第三者である専門家が、あなたの状況を客観的に説明し、企業側の不安を解消することで、よりスムーズな相互理解を促すことができます。
「安心して働きたい」を実現する企業選びと伝え方(合理的配慮)
障害者雇用において、長く安定して働くための鍵となるのが「合理的配慮」です。これは、障害のある人が他の従業員と平等に働けるよう、企業側が提供するべき配慮のことです。しかし、「何をどこまでお願いしていいのか分からない」「わがままに思われないか不安」と感じる方も少なくありません。ここでは、その不安を解消し、合理的配慮を前向きに活用するための知識とテクニックを提供します。
企業に求めるべき配慮の具体例
摂食障害の特性を踏まえ、IT業界で働く際に考えられる具体的な配慮の例を挙げます。これらはあくまで一例であり、あなた自身の特性に合わせてカスタマイズすることが重要です。
勤務環境に関する配慮
- 食事・休憩に関する配慮:
- 昼食を一人で静かに取れるスペース(自席や休憩室など)の確保。
- 体調に応じて、休憩時間を柔軟に(例:短く複数回)取得することの許可。
- 業務に支障のない範囲での、食事会や飲み会への不参加の容認。
- 勤務形態に関する配慮:
- 通院のための中抜けや時間単位での休暇取得の許可(フレックスタイム制の適用)。
- テレワークや在宅勤務の導入、あるいはその日数を増やすこと。
- ラッシュアワーを避けた時差出勤の許可。
業務内容に関する配慮
- 指示・コミュニケーションに関する配慮:
- タスクの指示を口頭だけでなく、チャットやメールなどテキスト形式でもらうこと。
- 一度に多くの指示を出すのではなく、タスクを細分化して一つずつ指示してもらうこと。
- 定期的な1on1ミーティング(短い時間でも可)で、業務の進捗や困りごとを相談する機会を設けること。
- 業務の調整に関する配慮:
- プレッシャーを感じやすい電話応対業務の免除、または頻度の軽減。
- 急な仕様変更や突発的な業務が少ない、比較的安定したプロジェクトへの配属。
- 過度なマルチタスクを避け、一つの業務に集中できる環境の整備。
上手な伝え方のコツ
必要な配慮を企業に効果的に伝え、受け入れてもらうためには、少しの工夫が必要です。ポイントは、「できない理由」ではなく「できるための条件」を提示することです。
- 「できない」ではなく「こうすれば、できます」と伝える:ネガティブな表現は、相手に「対応が難しい人」という印象を与えかねません。伝え方をポジティブに変換しましょう。
- NG例:「体調に波があるので、安定して働く自信がありません。」
- OK例:「体調に波があるため、タスクの優先順位を明確にしていただけると、ペース配分がしやすくなり、安定して成果を出すことができます。」
- 自己分析に基づく客観的な説明を心がける:感情的に「辛いんです」と訴えるのではなく、自分の特性を客観的に分析し、具体的な事実として伝えましょう。
- NG例:「電話がすごく苦手で、パニックになってしまいます。」
- OK例:「予期せぬ質問に即座に答えることが苦手で、強いストレスを感じる傾向があります。そのため、可能であれば、お問い合わせは一度メールでいただき、内容を確認してから対応させていただく形が望ましいです。」
- 支援機関という「第三者の視点」を活用する:自分一人で伝えるのが難しい場合、就労移行支援事業所のスタッフの力を借りるのが最も効果的です。就労支援機関の職員が同席し、「ご本人は〇〇という特性をお持ちですが、△△という環境であれば、これまでの訓練実績から見て、十分に能力を発揮できます」と客観的な情報として伝えることで、企業側も安心して受け入れ体制を整えることができます。これは、就労移行支援を利用する最大のメリットの一つと言えるでしょう。
まとめ:あなたの「もう一度」を、専門家と共に確実な一歩へ
この記事では、摂食障害からの回復期にあるあなたが、新しいキャリアとしてIT業界を目指すための道筋を、具体的なステップと共にお伝えしてきました。
柔軟な働き方、スキル本位の評価、そして論理的思考力が強みとなる業務特性。IT業界は、あなたが抱える困難を乗り越え、自分らしさを活かしながら社会と再び繋がるための、大きな可能性に満ちた場所です。しかし、その可能性を現実のものにするためには、正しい知識、計画的なステップ、そして何よりも、あなたの心と体に寄り添う専門的なサポートが不可欠です。
一人で全てを抱え込む必要は、もうありません。あなたの回復のペースに合わせ、スキル習得から、あなたに合った「居場所」である企業探し、そして就職した後も安心して働き続けられるよう、すぐそばで伴走する存在がいます。
あなたの「もう一度」を支える、リライトキャンパス浜松駅南
私たち、株式会社rewriteが2025年9月に浜松駅南に開所した「リライトキャンパス浜松駅南」は、単にITスキルを教えるだけの場所ではありません。私たちは、あなたの心と体の状態に深く寄り添い、一人ひとりに最適化された支援計画を通じて、「安心して、長く、自分らしく働ける未来」を一緒に創り上げていくパートナーです。
リライトキャンパス浜松駅南の約束
- 個別カウンセリングとオーダーメイド計画:福祉の現場で豊富な経験を持つサービス管理責任者が、あなたの体調や回復段階、目標を丁寧にヒアリング。あなただけの個別支援計画を作成し、定期的な面談で進捗を確認しながら、二人三脚で歩みます。
- 未経験からプロへ導くIT研修:「パソコン操作も自信がない」という方でも大丈夫。Webデザイン、プログラミング、Webマーケティングなど、現代のIT業界で需要の高いスキルを、あなたのペースに合わせて基礎の基礎からじっくりと学べます。
- 万全の就職・定着サポート:あなたの特性や希望に合った企業探しから、履歴書の添削、ポートフォリオ作成支援、面接での「合理的配慮」の伝え方の練習まで、徹底的にサポート。さらに、就職後も定期的な面談を通じて職場での悩みをフォローし、あなたが新しい環境にスムーズに適応できるよう支え続けます(定着支援)。
あなたの人生の新しい章を「書き換える(rewrite)」ための、最初の一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか。
まずは、あなたの不安や疑問、これからの希望について、私たちに聞かせてください。
話すことから、すべてが始まります。