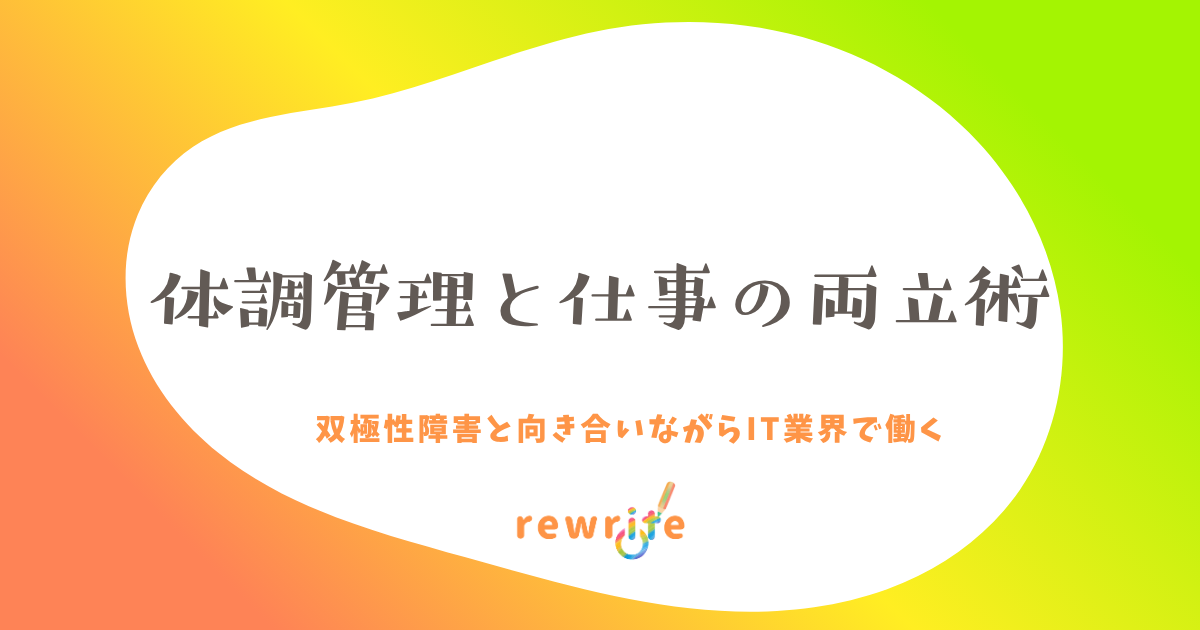「IT業界でキャリアを築きたい。でも、双極性障害の症状とどう付き合っていけばいいのだろう…」
技術革新が絶えず、刺激的でやりがいの大きいIT業界。しかしその一方で、高いプレッシャーや不規則な業務時間が、心身のバランスを崩すきっかけになることも少なくありません。特に、気分の波が特徴である双極性障害を抱える方にとって、この業界で安定して働き続けることは大きな課題と感じられるかもしれません。
しかし、諦める必要は全くありません。双極性障害のある人は、高い創造性、共感力、レジリエンス(回復力)といった強みを持つことが多いと指摘されています。適切な自己管理、職場環境の調整、そして専門的なサポートを組み合わせることで、IT業界はあなたの才能が輝く最高の舞台になり得ます。
この記事では、双極性障害と向き合いながらIT業界で自分らしく働くための具体的な方法を、体調管理と仕事術の両面から徹底解説します。そして、その実現をサポートする「就労移行支援」という選択肢についてもご紹介します。
双極性障害がIT業界でのキャリアに与える影響
IT業界は、双極性障害のある方にとって「諸刃の剣」となる可能性があります。その特性を理解し、課題と強みの両面を把握することが、キャリアを成功させる第一歩です。
特有の課題:高ストレスと不規則な環境
IT業界は、その性質上、精神的な負担が大きくなりやすい環境です。ある調査では、IT業界は過重労働や劣悪な心理社会的労働環境により、精神障害が発生しやすいことが指摘されています。
- 厳しい納期と高いプレッシャー:プロジェクトベースの業務が多く、タイトなスケジュールは日常茶飯事です。この絶え間ないプレッシャーは、気分の波を誘発する大きなトリガーとなり得ます。
- 長時間労働と不規則な生活:システムのリリース前やトラブル対応時には、深夜までの残業や休日出勤が発生しがちです。このような生活リズムの乱れは、双極性障害の症状を不安定にさせる最も大きな要因の一つです。
- 絶え間ない変化と学習:次々と新しい技術が登場するため、常に学び続ける姿勢が求められます。これが知的好奇心を満たす一方で、過度な情報量や変化への適応がストレスになることもあります。
あるITエンジニアは、軽躁状態の時に驚異的な集中力でプロジェクトを成功させ「マシーンのようだ」と賞賛されたものの、その裏では不眠不休で働き、後に深刻なうつ状態に陥ったという体験を語っています。これは、IT業界の環境が症状を増幅させ得ることを示す象徴的な例です。
強みとなる可能性:創造性と集中力
一方で、双極性障害の特性は、IT業界で求められる資質と合致する面もあります。「CEOの病」と呼ばれることがあるように、そのエネルギーや独創性が、時に大きな成果を生み出す原動力となるのです。
- 高い創造性:軽躁状態の時には、アイデアが次々と湧き、斬新な解決策やイノベーションを生み出すことがあります。これは、新しいサービスやプロダクト開発において非常に価値のある能力です。
- 驚異的な集中力と生産性:気分が高揚している時期には、寝食を忘れて一つのタスクに没頭し、短期間で驚くほどの成果を上げることがあります。適切にコントロールできれば、プロジェクトの推進力となり得ます。
- 共感力とレジリエンス:気分の浮き沈みを経験しているからこそ、他者の感情に敏感で、高い共感力を発揮することがあります。また、困難な状況を乗り越えてきた経験は、強い精神的な回復力(レジリエンス)につながります。
重要なのは、これらの強みを自覚し、気分の波に「乗っ取られる」のではなく、自分で「乗りこなす」ための戦略を持つことです。次のセクションでは、そのための具体的なセルフケア術を解説します。
仕事と両立するためのセルフケア戦略
IT業界で安定して働き続けるためには、自分自身で体調を管理し、安定した状態を維持する「セルフケア」が不可欠です。ここでは、今日から実践できる4つの重要な戦略をご紹介します。
1. 自分の「波」を知る:早期警告サインの把握
気分の波が本格的になる前に、その予兆(早期警告サイン)を捉えることが、症状の悪化を防ぐ鍵となります。自分の心と体の変化に敏感になりましょう。
- 気分の日記をつける:日々の気分、睡眠時間、エネルギーレベル、出来事などを記録します。これにより、自分の気分のパターンや、特定の出来事がどう影響するかが見えてきます。「eMoods」や「Moodfit」のようなアプリも便利です。
- 躁状態のサインを把握する:「あまり眠らなくても平気」「アイデアが次々湧いてくる」「おしゃべりになる」「お金遣いが荒くなる」などは、軽躁・躁状態への移行を示すサインかもしれません。
- うつ状態のサインを把握する:「体が重く、起き上がれない」「好きだったことに興味が持てない」「集中力が続かない」「食欲がない、または過食になる」などは、うつ状態のサインです。
これらのサインに気づいたら、意識的に休息を取る、信頼できる人に話す、主治医に相談するなど、事前に行動計画(アクションプラン)を立てておくと、冷静に対処できます。
2. 生活リズムを整える:安定の土台作り
双極性障害の管理において、規則正しい生活リズムは治療薬と同じくらい重要です。特にIT業界の不規則な働き方に対抗するため、意識的に体内時計を整える努力が必要です。
「対人関係・社会リズム療法」という心理療法では、生活リズムの安定が気分の安定に直接つながると考えられています。毎日のルーティンを確立することが、症状管理の土台となります。
- 睡眠リズムを死守する:平日・休日を問わず、毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることを目指しましょう。特に睡眠不足は躁状態の引き金になりやすいため、徹夜や極端な夜更かしは避けるべきです。
- 食事のリズムを保つ:1日3食、できるだけ決まった時間に食事をとることで、体内時計が整いやすくなります。
- 活動のリズムを作る:日中は太陽の光を浴び、適度な運動を取り入れることで、心身ともに活性化し、夜の寝つきも良くなります。
3. ストレス管理とリラクゼーション
ストレスは気分の波の大きな引き金です。自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常的に実践することが大切です。
- こまめな休憩:「疲れたから休む」のではなく、「疲れる前に休む」ことを意識しましょう。ポモドーロ・テクニック(25分集中して5分休む)なども有効です。
- リラクゼーション技法:深呼吸、瞑想、ヨガなどを日常に取り入れ、心と体を落ち着かせる時間を作りましょう。
- 仕事とプライベートの切り替え:仕事の始めと終わりに、ストレッチや好きな音楽を聴くなどの短い儀式(ルーティン)を取り入れると、オン・オフの切り替えがスムーズになります。
4. 治療の継続と専門家との連携
双極性障害は、適切な治療を継続することで、症状をコントロールし、安定した社会生活を送ることが可能な病気です。
- 自己判断で服薬を中断しない:症状が安定していると感じても、自己判断で薬をやめることは再発の大きなリスクとなります。薬の調整は必ず主治医と相談してください。
- サポートネットワークを築く:主治医やカウンセラー、信頼できる家族や友人など、自分の状態を理解し、いざという時に頼れる「チーム」を作っておきましょう。
職場環境の調整と活用術
セルフケアと並行して、働きやすい環境を自ら作り出していくことも重要です。職場選びから、入社後のコミュニケーションまで、戦略的に考えましょう。
職場の選び方:自分に合った環境を見つける
すべてのIT企業が激務というわけではありません。自分の特性に合った企業文化や職種を選ぶことが、長く働き続けるための鍵です。
- 避けるべき職場の特徴:
- シフト勤務や夜勤が多い職場:生活リズムが乱れやすく、症状の悪化に直結します。
- 個人の裁量が大きすぎる、または小さすぎる職場:躁状態で働きすぎる、うつ状態で何も手につかない、といった事態を避けるため、業務量やペースを相談・調整しやすい環境が望ましいです。
- 高いノルマや成果主義が極端な職場:過度なプレッシャーは避けましょう。
- 望ましい職場の特徴:
- フレックスタイム制やリモートワークが導入されている:体調に合わせて働き方を調整しやすいです。
- 業務量が比較的安定している:社内SE、品質管理(QA)、テクニカルサポートなど、比較的スケジュールが安定しやすい職種も検討の価値があります。
- チームで協力する文化がある:一人で抱え込まず、互いにサポートし合える環境は心強いです。
職場への開示(ディスクロージャー)と合理的配慮
病気のことを職場に伝えるかどうかは、非常にデリケートで重要な問題です。伝える義務はありませんが、伝えることで「合理的配慮」を受けやすくなるというメリットがあります。
- 開示のタイミング:もし伝える場合は、気分が安定している時に、冷静に事実を伝えるのが最善です。業務に支障が出始めてから慌てて伝えると、ネガティブな印象を与えかねません。
- 誰に、何を伝えるか:直属の上司や人事担当者に、まずは「業務に影響しうる健康上の課題がある」と伝え、必要な配慮を具体的に相談するのが一般的です。病名まで伝えるかは、相手との信頼関係や会社の文化を考慮して判断しましょう。
- 合理的配慮の例:
- 通院のための時間休や休暇の柔軟な取得
- 休憩時間の柔軟な設定(例:短い休憩を頻繁に取る)
- 時差出勤やリモートワークの許可
- 刺激の少ない静かな座席への変更
- 業務の優先順位付けや指示の明確化
合理的配慮は、障害者雇用促進法で定められた事業主の義務です。自分のパフォーマンスを最大限に発揮するために、必要なサポートを求めることは正当な権利です。
上司や同僚とのコミュニケーション
病気を開示する・しないに関わらず、日頃から円滑なコミュニケーションを心がけることが、働きやすさにつながります。
- 「報・連・相」を丁寧に:自分の業務の進捗状況をこまめに共有することで、万が一体調を崩した時にも周囲が状況を把握しやすく、サポートを得やすくなります。
- 働きすぎを抑制する仕組みを作る:躁状態で仕事にのめり込みがちな場合は、信頼できる同僚に「残業が続いていたら声をかけてほしい」と事前に頼んでおくのも一つの手です。
- 感謝を伝える:配慮やサポートをしてもらったら、必ず感謝の気持ちを伝えましょう。良好な人間関係が、何よりのセーフティネットになります。
就労移行支援:専門的サポートでキャリアを築く
「セルフケアや職場選びが重要だとわかっても、一人で全部やるのは不安…」
そう感じるのは当然のことです。そんな時に頼りになるのが、「就労移行支援事業所」です。
就労移行支援とは、障害のある方が一般企業で働くために必要な知識やスキルを身につけ、就職活動から就職後の職場定着までをトータルでサポートする福祉サービスです。
自分一人で悩むのではなく、専門家のサポートを受けながら、自分に合った働き方を見つけ、キャリアを築いていくことができます。
リライトキャンパス浜松駅南ができること
2025年9月、浜松市に開所した「リライトキャンパス浜松駅南」は、まさにIT業界を目指す双極性障害のある方を力強くサポートする就労移行支援事業所です。
リライトキャンパス浜松駅南のサポート
私たちは、一人ひとりの特性と希望に寄り添い、IT業界でのキャリア実現を全力で応援します。
- 個別カウンセリングを通じた自己理解:専門の支援員があなたの強みや課題、価値観を一緒に整理し、最適なキャリアプランを考えます。
- 実践的なITスキル習得:プログラミング、Webデザイン、IT事務など、あなたの目標に合わせたカリキュラムを提供します。
- 体調管理(セルフケア)プログラム:自分自身の気分の波を管理し、安定して働くための具体的なスキル(アンガーマネジメント、ストレスコーピング等)を学びます。
- 企業との連携による就職活動支援:履歴書添削や模擬面接はもちろん、あなたの特性を理解してくれる企業とのマッチングをサポートします。
- 安心の職場定着支援:就職後も定期的な面談を行い、職場で困ったことがあれば、あなたと企業の間に入って調整し、長く働き続けられるよう支援します。
「自分らしく、安定して働きたい」その想いを、私たちと一緒に形にしませんか?
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
双極性障害を抱えながらIT業界で働くことは、決して簡単な道ではありません。しかし、それは不可能な挑戦でもありません。
この記事でご紹介したように、
- 自分の特性を深く理解し、セルフケアを徹底すること。
- 自分に合った職場環境を選び、必要な配慮を求める勇気を持つこと。
- 一人で抱え込まず、専門家のサポートを積極的に活用すること。
この3つの柱を意識することで、気分の波を乗りこなし、あなたの持つ素晴らしい才能をIT業界で存分に発揮することができます。
もしあなたが今、キャリアについて悩み、一歩を踏み出せずにいるなら、ぜひ「リライトキャンパス浜松駅南」のような就労移行支援事業所を頼ってみてください。私たちは、あなたの「再挑戦(Rewrite)」を全力でサポートします。